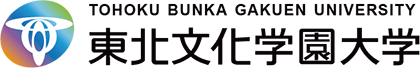木の声、土の歌(10)
総合政策学部教授 秡川 信弘
英国人に習ったという菓子作りを小学3年の夏休みに父に教えて貰った時のことを今も覚えている。幼い頃に父親を亡くした父は戦闘機の操縦士を夢見たが叶わず、㈱中島飛行機で働いた後に海軍を志願し、横須賀?呉での訓練を経て戦地に赴く。敗戦濃厚となった昭和19年、乗船した重巡が右舷を米潜水艦の魚雷に破砕されて昭南島(Singapore)に停泊することになり、終戦後は捕虜として2年余り空港建設の強制労働に服していた。
支配?制御する側の仮想現実(virtual reality)と対峙する支配?制御される側の現実(reality)。生きる心身は修羅にあっても、そこを突き抜けた先には美徳(virtue)が見えてくるかもしれない。ゲームサイトに嵌る君たちが探求しているものはどのような美徳なのだろうか。
生きるもののすべて、ヒトもムシも木も草も、いつかは生命活動という時間軸に沿った流れの終着点を迎え、活動を終えた個体は分子の統合体としての姿形を変貌させていく。私たちが未来を創造しうるのは約138億年と推定される宇宙史と比べれば極僅かな瞬間にすぎない、今ここに賦与された生命という猶予期間だけである。
生命体の集合である組織や社会に関する情報は文字や映像あるいは記憶やイメージなどさまざまな形で伝えられ、刻々と更新される情報の海の中で個体の生存期間を超えて存続しうる。海上に浮かぶか海底に沈むかの決め手はリアリティや画質ではなく、情報量でもないだろう。その浮沈は生きた証となる情報の質によって定まるはずである。
関東大震災の翌年(大正十三年)正月二十日、結核という不治の病に罹患した妹の死を看取ってから419日目にあたるその日、宮沢賢治は「春と修羅?序」の中に書いている。
(すべてがわたくしの中のみんなであるやうに
みんなのおのおののなかのすべてですから)
東京工業大学の世界文明センターに勤めていたPulversはneuronal networkに比定される「インドラの網」を翻訳機代わりに用い、賢治の難解な表現から時空を超えた宇宙意識を抽出してみせた。すなわち、「人間も自然もこの世を形成している分子のひとつ」にすぎず、「すべての分子は時間軸を超えて」互いに繋がり、善行も悪行も巡りめぐって我身に降りかかる因果応報の仕組みを構成する要素にすぎない、と。だが、敢えて自然の摂理を繰り返すことを許してもらえば、生身の人間は時空の制約を超えることはできない。
記録や歴史、あるひは地史といふものも
それのいろいろの論料といっしょに
(因果の時空的制約のもとに)
われわれがかんじてゐるのに過ぎません
科学的に取捨選択された素材(論料)から構築される事実は時空(4次元)の制約下に存在するものであり、同次元に存在する「われわれ」が感じているものでしかない。だが、人類はその制約を打ち破ろうと真理を探求し続けてきたのであって、科学とはいわばその結晶であり、象徴である。
巨大な生産力に衝き動かされた列強が世界戦へと邁進した時代的文脈(context)において、「春と修羅?序」に込められた含意(implication)とは、各々が自らの心の中に超歴史的な美徳(宝珠)を見出し、自然生態系を包摂する宇宙に繋がる存在としてそれを磨き続ける意志を求めようとする願いであったように思えてならない。
すべてこれらの命題は
心象や時間それ自身の性質として
第四次延長のなかで主張されます
みんなのすべてを修める学究(student)とは荒海に漕ぎ出し未知の生物を求める漁師ともいうべき存在であり、君たちのように、体感したことを記憶し、考え、表現し、交信する脳を介して繋がる網目のひとつである内なる宝珠を磨きながら、それに呼応して光り輝く他者の宝珠を求め、共に生きることを願わずにはいられないのだろう。
はてさて、賢治が想像した2,000年後の未来、人類が生存しているなら、どのような海で、いかなる生物を捕獲して暮らしているのだろうか。