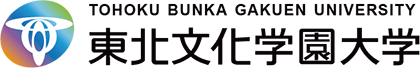クッキーの思い出
総合政策学部准教授 大野朝子
以前、アメリカに留学中の友人が、一時帰国の際に、お土産に沢山の料理本を持ってきてくれた。なかでも、分厚いペーパーバックの「料理の基本」の本は圧巻で、本格的フレンチから、エスニック料理まで、数百種類のレシピがこと細かに記載されている(写真やイラストは一切ない)。料理の「辞書」という感じだ。さすが、実用性を重んじる国の本だけある。
私にとっての典型的なアメリカの食べ物は、やはりクッキーである。二十代の頃、留学先のアメリカの大学の寮で、仲間たちと一緒に大量のチョコチップ?クッキーとピーナッツバター?クッキーを焼いたことがあった。手作りのお菓子は、ときに市販品とは比べものにならないほど美味しい。ホームステイ先のホストマザーが作ってくれた、即席のショートケーキも、英語の先生が特別に焼いてくれたクリスマス?プディングも、忘れられない味である。
フランスに旅行に出かけたとき、街角のパン屋のカウンターにさりげなく置かれたクッキーを買ってみたら、素朴な味わいに感激した。包装もシンプルで、ただビニール袋に入れただけ。丸いクッキー型で抜いてあるが、中には丸形が欠けたものも「堂々と」混入していた。あっさりした甘味が癖になり、旅行中は常に鞄に入れて持ち歩いたほどだ。
趣味が高じて、これまで大量のレシピ本やインターネットの情報をもとに、様々な種類のお菓子を焼いてきた。それでも「もっと何か珍しいものを作りたい!」と、お菓子作りへの情熱は前のめりになる一方であるが、最近、やっと自分の腕試しをする良い方法を見つけた。それは、「小説に登場するお菓子や料理を再現すること」である。
私が愛読しているアメリカの作家、トニ?モリスンの小説には必ず料理上手な女性が登場する。食事のシーンは、作る側、食す側にとって、無言の大切なコミュニケーションの時間である。モリスンの『ビラヴド』では、主人公セサが、十八年ぶりに再会した友人をもてなすため、急いでビスケットを焼く。粉とラードを混ぜる動作と、ビスケットの膨らみ具合の描写が、セサの喜びを象徴するようで、いつまでも心に残った(その友人は、のちに彼女の恋人となる)。そこで翌日、さっそくビスケット作りに挑戦。セサが焼いたビスケットには劣るかもしれないが、まずまずの出来に満足し、大好きなモリスンの世界へ一段と近づいた気がし、ひとり満足した。