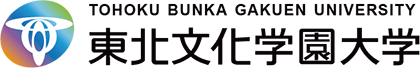『日米避戦交渉にかけた男』を読んで
総合政策学部教授 貝山 道博
日本列島全体が猛暑に襲われたこの8月のある日、一冊の本が送られてきた。岩城求著『日米避戦交渉にかけた男 井川忠雄と「日米諒解案」』(株式会社ウインかもがわ出版、平成27年8月15日発行)である。著者とは大学時代同じゼミに所属し、2年間一緒に学んだ仲である。先生には研究者の道へ進んだらと誘われたようであるが、実家が農業を営んでいることもあって、農業の発展のために尽くしたいということで、農林中央金庫へ就職した。
井川忠雄は、農林中央金庫の前身である旧産業組合中央金庫の理事であった(もともとは大蔵省の役人)。著者の大先輩にあたる。井川忠雄は一民間人でありながら、当時の近衛文麿首相の意を受けて(?)、太平洋戦争勃発直前、昭和16年の2月13日避戦交渉のために渡米するが、目的を果たせず、失意の想いで同年8月15日に帰国する。
岩城氏がなぜ井川忠雄に出会ったのか、そのことは本書には書かれていない。岩城氏とのこれまでの話から想像するに、太平洋戦争を冷徹に見つめてみようという彼の継続的努力が、結果的に井川忠雄に辿りつかせたのだろう。
本書の内容については、皆さんに直接お読みいただくとして、ここでは紹介しない。野村?来栖大使対ハル国務長官の日米交渉だけが、取り上げられがちであるが、民間レベルでの交渉(もちろん避戦交渉)も行われていたという歴史的事実は無視され過ぎていると、著者は嘆く。一時「日米避戦諒解案」が日本の政府統帥部連絡会議でも基本的には了承されていたが、日米双方の事情でこの案が正式な交渉のテーブルに載せられることはなかった。極東国際軍事裁判(いわゆる東京裁判)でもこの事実は連合国側に完全に無視されている。
歴史には「もし」はないが、仮に避戦協定が締結されたとしたら、その後の日本の辿るべき道はどう変わったのであろうか。想像したくなるところである。
終戦の日の8月15日、この本のお陰でこれまでとは少し違った思いでこの日を過ごすことができた。